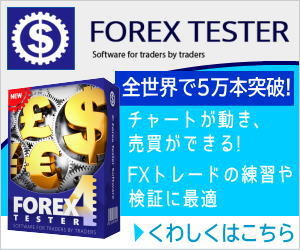「1回のトレードにどれだけのリスクをかけるか?」は、勝てる手法よりも成績を左右する資金管理のコア設計です。本記事では、固定%法・ボラティリティ調整・ケリー基準(Kelly Criterion)という三つのアプローチを比較し、ドローダウン耐性と破綻確率の観点から実務的な目安を導きます。
もくじ
この記事のゴール
読了後に、あなたは次の3点を即日で実装できます。
- (1)自分の口座に適したリスク%を決める
- (2)ボラティリティに応じてロットを自動調整する考え方を理解
- (3)ドローダウンの深さと回復日数を事前に見積もる
リスク%とは?
ここで言う「リスク%」は、損切りに到達した場合に口座残高から失われる割合です。例:口座100万円、リスク1%=1万円を1トレードに賭ける、という設計です。利益は「伸ばせるだけ伸ばす」が基本ですが、損失は「設計通りに限定」するのが資金管理の根幹です。
大きく勝つ自由は、損失を小さく制御する規律から生まれる。
結論:おすすめの目安
統計的に見て、1回あたり0.5%〜1.0%は多くの手法・口座サイズでバランスが良いです。裁量初心者、EAの検証初期、連敗が心理に響きやすい時期は0.25%〜0.5%に落としても十分に成長可能です。攻めたい時期や、勝率×RR(リスクリワード)が明確に高いセットアップでは一時的に1.5%(上限2%)まで上げる余地はありますが、2%超えは累積損失の加速に注意が必要です。
大切なのは「常時ハイリスク」ではなく、基準は保守的に、例外はデータに裏付けられた優位性に限定することです。
決め方の3アプローチ
1)固定%法(Fixed Fractional)
口座残高に一定割合(例:1%)を常にかける方法。残高が増えれば自動でロットが増え、減ればロットが減るため、複利効果と生存性のバランスが良い定番手法です。
2)ボラティリティ調整
同じ1%でも、損切り幅(pips)が広いとロットは小さく、狭いとロットは大きくなります。ATR(Average True Range)や標準偏差で相場の荒さを測り、想定損切り幅=k×ATRのように決めると、日によるリスク偏りを抑制できます。
3)リスク・バジェット(ポートフォリオ目線)
複数通貨・複数手法を運用する場合は、同時保有の相関を考慮し、総リスク%の上限(例:同時建て合計で3%以内)を決めます。これにより、「全部同方向に動いて想定外の損失」という事故を防げます。
ケリー基準を安全に使う
ケリー基準は、長期平均成長率を最大化するリスク配分です。勝率をp、損益比(平均利益÷平均損失)をbとすると、f* = p - (1 - p)/b が理論的な最適比率となります。
- 半ケリー(0.5×f*)… 過剰なボラティリティを抑え、現実的に使いやすい。
- 分母に不確実性… 勝率・損益比は推定値。誤差を見込んでさらに半分にするのが実務的。
要点は「ケリーは上限の目安」。固定%法の基準を持ち、十分な検証で優位性が計測できた戦略に限定して、基準+αとして活用しましょう。
ロット計算の手順
- 口座残高を確認(例:
Equity = 1,000,000円)。 - 1回のリスク%を決定(例:
risk = 1.0%)。 - 損切り幅を算出(テクニカル根拠、例:
SL = 25 pips)。 - 1 pip あたりの価値を把握(通貨・銘柄に依存)。
- ロット = Equity × risk ÷ (SL × pip価値) を計算。
例:USDJPY、1万通貨で1pip=100円と仮定、Equity=1,000,000、risk=1%、SL=25のとき、許容損失=10,000円、必要ロット=10,000 ÷ (25×100)=0.004(= 4千通貨)となります。
銘柄によってpip価値が違うため、取引プラットフォームのロット計算機や、EA/スクリプトの自動計算を推奨します。
実例とケーススタディ
ケースA:連敗に強くしたい(初心者・裁量)
基準リスクを0.5%にし、最大でも1%に限定。検証未熟なセットアップは0.25%。これで心理的ストレスを抑え、学習速度を落とさずに継続できます。
ケースB:EAの配布前テスト
ウォークフォワードやモンテカルロで最悪連敗を推定し、最悪連敗×リスク%で想定ドローダウンを見積もる。公開前は0.5%、安定後は1%へ段階的に昇格。
ケースC:高RRのブレイク戦略
統計的にRRが高く勝率が波打つタイプは、通常0.75〜1.25%。強い優位性ポイント(例:イベント後の一方向トレンド)だけ1.5%まで許容。
ドローダウンと破産確率
下表は、独立試行の近似で直感を得るための目安です(実運用では相関・スリッページ等で変動)。
| 1回のリスク% | 10連敗時の資産減少 | 20連敗時の資産減少 | 平均回復必要勝ち数(RR=1:1仮定) |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 約2.5%減 | 約4.9%減 | 約5〜6回 |
| 0.50% | 約4.9%減 | 約9.6%減 | 約11〜12回 |
| 1.00% | 約9.6%減 | 約18.2%減 | 約23〜25回 |
| 1.50% | 約14.0%減 | 約26.1%減 | 約35〜38回 |
| 2.00% | 約18.3%減 | 約33.2%減 | 約50回前後 |
ポイントは、回復に必要な勝ち数が非線形に増えること。2%は決して「危険」ではありませんが、損益の振れ幅と心理負荷は大きくなります。
運用ワークフロー(テンプレ)
- 月初に基準リスク%を設定(例:0.75%)。
- 毎トレードでATRベースのSLを算出しロット自動調整。
- 連敗が基準超過(例:7連敗)で半分にデレバ、回復で元に戻す。
- 月末に勝率・平均RRを更新し、半ケリーと比較して再評価。
この「規律×適応」の両立が、生存と複利成長の鍵です。
よくある質問
Q. 口座が小さいと1%では利益が小さすぎます。
A. 資金を増やす代替として、時間の複利(頻度×期待値)で積み上げるのが現実解。無理な%増は破綻率を上げます。
Q. 経験則で「2%ルール」を聞きました。
A. 2%は上限の一例であって万能ではありません。手法の分散・相関、心理耐性に合わせて0.5〜1%へ下げる選択は合理的です。
Q. ケリーは危なくない?
A. 推定誤差と現実の滑りを考慮して半ケリー以下を厳守。固定%法の基準を外さないのが前提です。
チェックリスト(保存版)
- □ 今月の基準リスク%は?(0.5〜1%)
- □ 連敗時のデレバ規則は定義済み?
- □ ATRや標準偏差でSL幅を定義している?
- □ 同時保有の総リスク%上限(例:3%)を設けている?
- □ 勝率・RRの更新頻度(月次)と半ケリーの再評価を行っている?
まとめ
リスク%は「生存率のダイヤル」です。まずは0.5〜1%の保守的な基準で生存と複利を確保し、データが揃った戦略にだけ限定的にリスクを増やす。ボラ調整とデレバ規則を添えれば、資金曲線はなめらかになり、目標到達までの時間は短縮できます。規律ある小さな損失は、将来の大きな自由の前払いです。