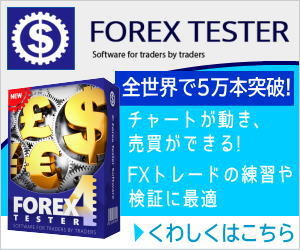もくじ
この記事の狙い
MACDとRSIは「キャラの違う便利屋」です。MACDはトレンドの持続力や転換の気配を、RSIは短期の過熱感や押し・戻りの圧力を可視化します。
同じチャートでも見る角度が違うため、得意な仕事も失敗パターンも異なります。本記事では「どの相場でどちらを主役にするか」「どの設定と組み合わせが効くか」を、
初心者にも再現できるレベルまで噛み砕いて解説します。
重要なのは、インジケーターそのものより相場環境の診断です。
トレンド相場では追随の根拠が欲しく、レンジ相場では反転の根拠が欲しい——この欲求の違いが、使い分けの起点になります。
基本:MACDとRSIの役割
MACDとは
MACD(Moving Average Convergence Divergence)は、2本の指数平滑移動平均(EMA)の差分から生まれる「勢い指標」です。
一般的な初期設定は12, 26, 9。ヒストグラムの拡大・縮小や、シグナルラインとの交差でトレンドの加速/減速や転換の初動を捉えます。
RSIとは
RSI(Relative Strength Index)は上昇幅と下落幅の比率から作られる「相対的な強弱」を示すオシレーターです。
初期設定は14が有名。一般に70以上は買われ過ぎ、30以下は売られ過ぎの目安ですが、環境で閾値は変えます。
特にレンジ判定や押し目/戻り目の可視化が得意です。
計算と読み方のポイント
MACDの読み方
- ヒストグラムの拡大はモメンタム増加、縮小は減速のサイン。
- ゼロライン越えはトレンドの地合い変化。上抜け後の押し(下抜け後の戻り)は強い。
- 価格が高値更新でもMACDが高値更新しない場合は弱気ダイバージェンス。
RSIの読み方
- レンジでは70/30のバウンドが効きやすい。トレンドでは50ライン付近の支え/抵抗に注目。
- 上昇トレンド中はRSIの下限を40〜50に引き上げ、下降トレンド中は上限を50〜60に引き下げるとノイズが減る。
- 価格が安値更新でもRSIが安値更新しない場合は強気ダイバージェンス。
比較表:得意・不得意と注意点
| 項目 | MACD | RSI |
|---|---|---|
| 得意な相場 | トレンドの発生・継続局面で強み。押し目/戻りの再加速判定。 | レンジ相場や短期の逆張り判断。過熱感の可視化。 |
| 苦手な相場 | 狭いレンジのノイズやだまし。遅行で初動を逃すことも。 | 強トレンドの張り付き。過熱サインで早逃げしやすい。 |
| 主な指標値 | 12, 26, 9(市場と時間軸で調整) | 14(市場と時間軸で調整) |
| 相性の良い補助 | 移動平均、ボリンジャー、出来高モメンタム | サポレジ、ピボット、ストキャス、ATR |
| 判断の軸 | モメンタムの方向とゼロライン | 中立値(50)と上下閾値 |
| 注意点 | EMA期間が長いと一歩遅れやすい | 閾値固定は環境変化に弱い |
相場環境での使い分け
トレンド相場
主役はMACD。ゼロライン上(下)でヒストグラムが再拡大する押し目(戻り)を狙います。RSIは50近辺の反発確認の補助として使い、
「過熱だけで早逃げしない」ことがコツ。利確は直近のスイング、またはMACDの減速(ヒストグラム縮小)を手仕舞い条件に。
レンジ相場
主役はRSI。上下バンドや水平線と併用し、70/30の極端値付近からの反転を狙います。MACDはゼロ近傍でノイズが増えるため、
フィルターとしての優先度は下げます。
ボラティリティが急変する局面
ATRや標準偏差などボラ指標で環境を先に診断。急拡大ではMACDのシグナル遅延が増すので、短期RSIで過熱を監視しつつ分割決済やトレールを併用します。
時間軸による使い分け
- 短期(1分〜5分):RSIの機動力が活きる。MACDは期間を短縮(例:8, 21, 5)して初動感度を上げる。
- 中期(15分〜1時間):MACDの地合い判定が有利。RSIは50ラインを基準に押し戻りの精度を上げる。
- 長期(4時間〜日足):MACDで大局の流れ、RSIで押し戻りゾーン。順張りの優位が高い。
マルチタイムフレーム(MTF)では、上位足のMACD地合いに沿って、下位足のRSIでタイミングを詰めるのが王道です。
実戦ルール例(エントリ/利確/損切)
順張り・トレンドフォロー例
- 上位足(1時間)のMACDがゼロ上で拡大中。
- 下位足(5分)でRSIが50〜55付近から再上昇。
- 直近高値ブレイクで成行または逆指値エントリ。
- 損切は直近スイング下。利確はR=1.5以上、またはMACD減速で分割決済。
逆張り・レンジ回帰例
- 水平レンジを確認(高安の更新が止まっている)。
- RSIが70付近から反落(売り)/30付近から反発(買い)。
- ダマシ防止に小さな戻り(押し)を待ってから指値エントリ。
- 損切はレンジ外。利確はレンジ中心または反対側のバンド。
ダイバージェンス活用
MACDとRSIはどちらもダイバージェンス検出に使えます。MACDはモメンタムの鈍化、RSIは相対強弱の反転。
価格と指標の高安更新の不一致は「終わりの始まり」を示すことが多く、トレンド転換の初動を拾うヒントになります。
ただし単発では弱いので、水平線・出来高・ローソク足の形など複数根拠で強化しましょう。
組み合わせ方とフィルター設計
原則は「MACD=地合い/モメンタム」「RSI=タイミング/過熱」。片方は方向、もう片方は押し/戻りに使い分けます。
フィルターとしては、移動平均(トレンド方向)、ボリンジャーバンド(ボラと逆張りゾーン)、ATR(損切幅調整)を最小構成に。
設定の目安:短期はMACD(8,21,5)+RSI(7〜9)、中期はMACD(12,26,9)+RSI(14)、長期はMACD(19,39,9)+RSI(21)。
あくまで起点なので、銘柄のクセに合わせて最適化してください。
チェックリスト&よくある誤り
- 環境認識を先にやったか?(トレンド or レンジ)
- 上位足の方向に沿っているか?(逆張りなら根拠を2つ以上)
- MACDはゼロ上(下)で拡大中か、減速中か?
- RSIは50ラインの位置関係と上下閾値を動的に調整したか?
- エントリ前に損切位置と想定Rを決めたか?
- 決済は分割+トレールで計画したか?
ありがちな失敗
- RSIの70/30をトレンド相場でも固定して逆張りし続ける。
- MACDのクロスのみでエントリし、ボラ急変で振り回される。
- 上位足の地合いを無視して下位足だけで判断する。
まとめ
MACDは地合いとモメンタム、RSIは過熱とタイミング。この役割分担を守るだけで余計な敗戦が減ります。
相場はいつも同じ顔ではありません。環境に応じて閾値や期間を柔軟に変え、上位足で「向き」を、下位足で「入る瞬間」を決める。
シンプルですが、習熟すると武器になります。
付録:よくある質問
Q. 強トレンドでRSIがずっと高止まりします。
A. 正常です。上昇トレンドではRSIの下限を40〜50に、下降では上限を50〜60に移し、
50ラインの押し戻りで順張りする発想に切り替えましょう。
Q. MACDが遅くて初動に乗れません。
A. 期間を短縮する、下位足のRSIで先行サインを拾う、ブレイクは逆指値で待つなど、
「感度を上げる+待ち伏せ」をセットで改善します。
Q. ダイバージェンスはどれを信じれば?
A. 上位足の水平線・出来高・ローソク足パターンと重なる箇所を優先し、単発は回避。
収束三角やラストスイング近辺のものは質が高い傾向です。